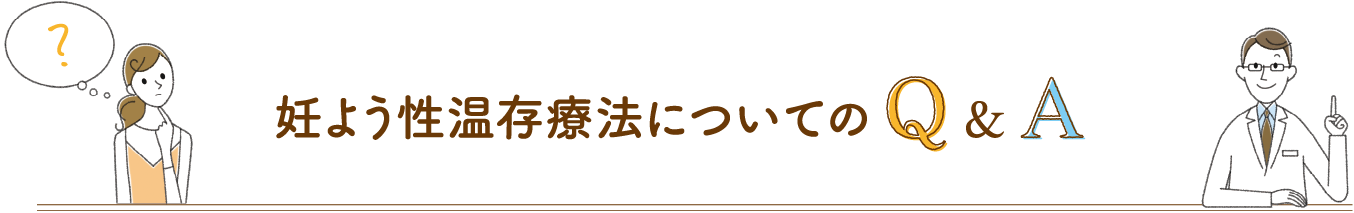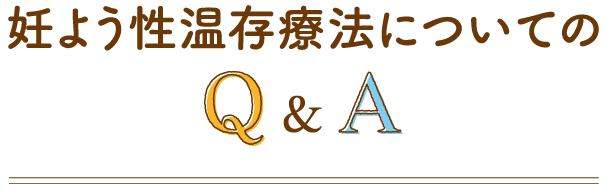ついてのQ&A
妊よう性温存についてはだれに相談すればよいでしょうか。
-
誰にも相談できず悩んでしまう場合があるかもしれませんね。
がん治療担当医に相談しにくい場合には、医療機関内にある相談支援センターやがん診療連携室などのがん相談窓口、あるいは看護師さんなどに相談してみてはいかがでしょうか。 どういうタイミングで相談すればよいでしょうか。
-
妊よう性温存療法は、がんの治療が始まる前に行います。
がんと診断されたばかりでは何も考えられないかもしれませんが、まずはどのような選択肢があるのか、できるだけ早めに相談することをお勧めします。
すでに、がん治療が始まっている方で、妊娠・出産に関する不安がある方は、がん治療担当医や、看護師さんなどに相談してみましょう。 -
がん治療終了後は、妊よう性温存療法の実施有無にかかわらず、産婦人科や泌尿器科を受診したほうがよいでしょうか。
-
受診することをお勧めします。がん治療の種類によっては卵巣や精巣にダメージを与えることがあり、その影響は症状としてわかりづらいことがあります。
また、性線機能自体が年代によって変化していくため、健康管理や今後のライフプランのためにも、あなたが受けたがん治療の内容と現在の状況を産婦人科医や泌尿器科医に評価してもらうことは大切です。 -
妊よう性温存療法にはどれくらいの期間がかかりますか。
-
凍結保存までにかかる期間の目安は、卵子、胚の場合は2~6週間、卵巣組織の場合は1週間です。
-
妊よう性温存療法はどれくらい費用がかかりますか。
-
妊よう性温存療法は保険適用外のため、すべて自費診療となります。採取の方法によって費用は異なりますが、卵子の凍結保存は20~40万円くらい、胚の凍結保存は30~50万円くらい、卵巣凍結保存では60~80万円くらいかかります。初期費用のほかに、維持費用として毎年数万円程度かかります。また、妊娠をするための顕微授精や、胚移植、卵巣組織移植には、別途費用がかかります。
「厚生労働科学研究費補助金がん対策推進総合研究事業 小児・若年がん長期生存者に
対する妊孕性のエビデンスと生殖医療ネットワーク構築に関する研究」班:
がん治療を開始するにあたって<抗がん剤編>将来出産を希望される女性患者さんへ:
https://www.j-sfp.org/ped/index.html(2025年5月参照)
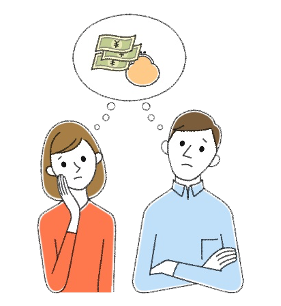
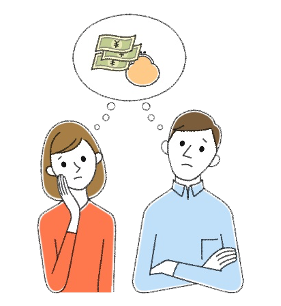
-
費用を補助してくれる制度はありますか。
-
自治体で助成金制度があります。治療を希望する場合にはお住まいの自治体によって助成上限額が異なる場合がありますので、詳細はお住まいの自治体窓口にお尋ねください。
-
温存療法により保存したあとの妊娠に向けた生殖補助医療について補助してくれる制度はありますか。
-
自治体で助成金制度があります。治療を希望する場合にはお住まいの自治体によって助成上限額が異なる場合がありますので、詳細はお住まいの自治体窓口にお尋ねください。
-
生殖医療機関はどのように探せばよいでしょうか。
-
まずはがん治療担当医に相談してください。連携している生殖医療機関がある場合があります。
下記の情報サイトをご参照ください。
【医療費の一部を助成する『小児・AYA世代がん患者等妊よう性温存療法研究促進事業』の指定医療機関】
https://outcome2021.org/(2025年5月参照)
(各自治体のホームぺージも合わせてご確認ください。) -
妊娠を希望する場合、出産したい病院は自由に選択できるのでしょうか。
-
病院によっては、生殖医療機関と連携されていないと受け入れられない場合があります。
-
妊よう性温存療法を受ける場合、どれくらいの期間凍結保存をしてもらえますか。
-
卵子、胚、卵巣組織、精子の保存期間は、ほとんどの施設で1年毎に、各施設で定めた期間内に手続きをすれば延長できます。
卵子、胚は女性の生殖年齢の範囲内で、延長が認められています。 -
妊よう性温存療法によって、子どもが生まれる確率はどれくらいですか。
-
一般的な不妊患者さんにおける2022年に国内で治療を受けた方の出産率は、凍結卵子を用いた方は10.2%(20/196回)、凍結胚を用いた方は27.0%(70,269/259,905回)でした。
日本産科婦人科学会主導臨床研究:令和5年度倫理委員会 登録・調査小委員会報告
表9 凍結融解未受精卵を用いた治療成績[2022年]、表8 凍結胚を用いた治療成績[2022年](2024年11月) -
遺伝性がんの可能性があっても、妊よう性温存療法を受けられますか。
-
遺伝性乳がん卵巣がん(HBOC)症候群やリンチ症候群など、遺伝性腫瘍(しゅよう)の可能性が高い場合も、妊よう性温存療法を受けることができます。ただし、生まれた子どもが同じ遺伝子異常を有する可能性もありますので、不安な場合は、パートナーや周りの方などとよく相談しながら考えましょう。
-
妊よう性温存療法を受けることが難しい場合、ほかの選択肢はありますか。
-
妊娠・出産を望むことが難しい場合、「里親・養子縁組制度」という選択肢もあります。
詳しくはこども家庭庁のHPをご参照ください。
【里親制度】
https://www.cfa.go.jp/policies/shakaiteki-yougo/satooya-seido
【特別養子縁組制度】
https://www.cfa.go.jp/policies/shakaiteki-yougo/tokubetsu-youshi-engumi
(2025年5月参照)