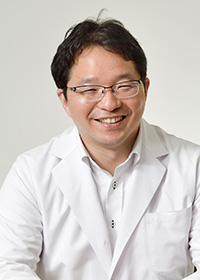会社に提出する4つの書類について
はじめに
就業中の方ががん治療のために、仕事をお休みすると決めた際、会社から様々な書類の提出を求められると思います。会社から求められるままに、深く考えずに書類を提出している方も多いようです。ここでは、会社が要求する書類について解説します。以下の4つの分類があることが一般的です。
会社から提出を求められる4つの書類
- 休業(休職)するための診断書(以下、休業診断書)
- 職場復帰するための診断書(以下、復職診断書)
- 職場復帰する際に必要な就業上の配慮が記載された意見書(以下、復職意見書)
- 傷病手当金を得るための申請書(傷病手当金申請書)
それぞれの書類の性格が違うため、目的に応じて適切に主治医に記載してもらうことが必要です。
休業診断書

がん治療を受ける場合、仕事を一定期間お休みして治療に臨む方が多いのではないかと思います。その際、会社に休業願いとともに休業診断書を提出することが必要になります。まず、病気による休業は法律で認められている制度ではなく、会社ごとの制度として制定されていることを理解しましょう。病気休業は一般的には、「治療を終えた段階で職場復帰することを前提として、仕事を休んで治療に専念する」ことが目的です。この書類は「休まなければならないやむを得ない体調」であることを主治医に証明してもらうことが必要になります。
休んでいる期間の詳細な体調については、会社にとっては何かすることができるわけではないので、あまり重要な情報とは言えません。したがって、詳しい病状まで記載することは要求されないことがほとんどです。病名と休業が必要な期間が記載されていることが重要になります。例えば、『○○がんの治療ため、○月○日まで休業が必要である』という記載が一般的です。休業診断書は人事手続き上、上司・人事・事業者など多くの人の目に触れがちです。どうしてもがんであることを伝えたくない場合には、腫瘍、腫瘤など、主治医が工夫して記載することになりますが、会社によっては不確実な記載を受け取ることで不安を募らせるケースもあるため一長一短であると言えます。
復職診断書
職場復帰する際には、職場復帰願いとともに、復職診断書を提出します。職場復帰は休業と反対で、「休まなければならない体調だったものが業務に戻ることができるようになった」ということを証明することが必要になります。こちらも、業務ができることになったことを証明してもらうことが目的の書類です。つまり、「○○がんの治療を行い経過良好のため、○月○日から復職可能である」という記載をしてもらうことが重要です。職場復帰するにあたり、何らかの配慮が必要な場合には、次の項目で説明する復職意見書に記載してもらうことになります。復職診断書も休業診断書と同様に人事手続き上、上司・人事・事業者などが確認するケースがほとんどです。
復職意見書
診断書と意見書の違いは一般的にはあまり知られていません。労働衛生の分野では、「医師の診断」とは、異常なし、要観察、要治療等の医学的に必要な措置について記載されることを指します。一方、「医師の意見」とは、通常勤務可、要就業制限(配慮)、要休業など業務に関連した注意点を述べることを指します。つまり、診断書は医学的な診断が記載されているもので、意見書は就業に関連して必要な配慮事項等が記載されているものということになります。両者は本来、別の書類ですが、意見書は診断書と同時に提供されることも多いです。「事業場における治療と職業生活の両立のためのガイドライン」(以下、ガイドライン)では、主治医と何度もコミュニケーションをとる手間を考慮し、一度で済ます書式(職場復帰の可否について主治医の意見を求める際の様式例)となっています。
主治医に就業上の配慮を述べてもらうためには職場の事情を知ってもらう必要があります。可能であれば職場の方から「職務情報に関する職場からの情報提供」を主治医に提供してもらうといいでしょう。こちらの書式もガイドラインに記載されていますので(勤務情報を主治医に提供する際の様式例)使ってみるといいでしょう。復職意見書は就業制限(配慮)に関連または影響のある人にだけ共有をお願いすることが可能です。
一般的に事業者が労働者を職場復帰させるときに最も注意を払っているのが、安全配慮義務に関連することです。安全配慮義務は仕事をすることで病状が悪化したり、事故を起こしたりすることを予防する義務で、事業者に課せられています。
一方で、労働者にとって大事なことはほかにもあります。治療中であっても働きやすい環境を整備してもらいたいという観点です。治療をすると、合併症や副作用により、疲れやすくなったり吐き気がしやすくなったりして、働きにくさを感じるようになることがあります。障害による働きにくさを解決するために、労働者自身が申し出て職場環境を改善してもらう配慮のことを合理的配慮と言います。合理的配慮は障害者差別解消法で規定されており平成28年4月から施行されています。これらは同じ配慮という言葉が用いられていますが、意味合いが違いますので注意が必要です。
傷病手当金申請書
業務出来なくなってから4日目以降は健康保険組合から傷病手当金が支給されます。支給期間は1年6か月間です。傷病手当金申請書は、これを申請するための書類です。ここで重要なのは、4日目以降から支給されるというところです。業務ができなくなってから連続する3日間の休みがない状況で退職した場合には、傷病手当金はもらえません。治療費や生活費のことも考えると、診断されていきなり辞めるという選択肢はできる限り避けた方がいいと言えるのではないでしょうか。
おわりに
書類以外にも休業するときに職場から得ておいた方がいい情報として、休暇日数が挙げられます。有給休暇日数(うち、時間単位で取得可能な日数)・休業日数・休職日数・ストック休など会社ごとに様々なルールで運用されており、自分がどれだけ休むことができるのか知らない労働者も多くいます。
ここに記載した書類はあくまで一般的なことで、会社によって取り扱いに多少の差異があります。しかしながら、会社が労働者の健康情報を収集する場合には、目的を明示したうえで本人同意を得て収集するという大原則があります。また、会社は収集した個人情報についてだれがどの情報を収集するかという点も事前に明示することが求められています。会社から過度な要求をされていると感じたら、「どのような目的でその情報が必要なのでしょうか?」と聞いてみるのも一案です。その際、感情的にならないように信頼のおける上司・同僚などに相談しながら進めることをお勧めします。
また、労働者自身にも業務ができるよう体調管理をする努力義務もあります。職場に配慮をお願いするばかりでなく、自身もできる限りの体調管理を行い就業できるように努め、お互いが理解しあうことが望まれます。
(2019年2月公開/2025年11月更新)
参考
厚生労働省、健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針(改正 平成29年4月14日健康診断結果措置指針公示第9号)https://jsite.mhlw.go.jp/kyoto-roudoukyoku/var/rev0/0123/9698/KE_20170419A.pdf、2025年10月22日閲覧