お金や支援制度、暮らしの相談もチームであなたを支えます~勤医協中央病院 がん相談支援センター
医療の進歩により、治療成績が向上する一方で、高額な治療も増えています。患者さんにとっては、経済的な負担が大きな悩みとなります。また、医療費の心配以外にも、仕事や介護との両立、日々の暮らしへの不安など、さまざまな悩みを抱えることも少なくありません。
勤医協中央病院では、医師はもちろん、がん相談支援センターのスタッフ(ソーシャルワーカーや看護師)やリハビリの専門職など、院内の多職種が連携し、こうした悩みに寄り添っています。今回は、がん相談支援センターや診療の現場で活躍するスタッフの方々にお話を伺いました。(2025年8月取材)

行沢 剛 さん(医療福祉部 部長 左から2人目)
剱持 喜之 先生(副院長 右端)
自分らしくがんと向きあえる病院と社会を目指す
剱持先生:当院は“無差別平等”を理念に掲げています。差額ベッド代はいただいていませんし、無料低額診療事業の認定医療機関でもあり、経済的な理由で治療を諦める患者さんを一人でも減らすことを目指してきました。他院で治療を受けていたものの経済的な問題で継続が難しくなり、当院に転院して治療を続けられたケースもあります。
もうひとつ大事にしているのは、“自分らしくがんと向きあえる病院と社会を目指す”というビジョンです。そのために、何よりも患者さんとの“対話”を重視しています。私が呼吸器内科医として診断や治療方針をお伝えする場面では、がん相談支援センターのスタッフ(看護師他)が同席し、患者さんがどう受け止めたかを一緒に確認してもらっています。
岡本さん:診察のときは、患者さんが医師に直接言いにくい思いを抱えていることもあります。そういうときに私たち看護師が聞き取り、医師やソーシャルワーカーにつなぐことがあります。
がん相談支援センターと各職種の役割「患者さんの思いを引き出し、支援につなげる」

患者さんのお話を伺う様子
剱持先生:医師や薬剤師はエビデンス(科学的根拠)に基づく治療を、きちんと患者さんに届ける役割が大きいですが、生活面の充実、特にその人らしく生きることを支えるのは看護師やソーシャルワーカー、セラピスト(理学療法士他)の得意分野だと思います。
山下さん:私たちが行うリハビリテーションは、毎日20〜40分間同じ患者さんと向き合うので、徐々に信頼関係が深まり、治療や生活の不安、医師に聞けなかったことを話される方もいらっしゃいます。そこで患者さんから聞いた声を看護師や主治医に伝える橋渡し役となることがとても多く、そこで伺った困りごとなどを、解決できそうな専門職につなぐことが、治療継続を支える大切な役割だと感じています。
剱持先生:医師の立場からも、セラピストからの情報はとても貴重だと感じています。生活に関わることや「こうしたい」という患者さんの希望が含まれていることが多く、治療方針を決めるうえで大きな助けになります。
行沢さん:ソーシャルワーカーである私と看護師の岡本さんは、主にがん相談支援センターで活動しています。相談を受けるタイミングとして、大きく二つの場面に分けられます。
ひとつは外来診療の場面です。告知を受けた直後や抗がん剤治療を始めるときに「どれくらい医療費がかかるのか?」と相談される方が多いです。
もうひとつは入院中で、「入院費はどのくらいかかるのか?」、「退院してから一人で暮らせるか?」といった不安が出てきます。そのようなときには、費用面の悩みだけでなく、介護サービスについての相談に乗ることもあります。
岡本さん:以前、がんと診断された患者さんで、入院をためらっていた方がいらっしゃいました。理由を伺うと、自宅に介護が必要な家族がいたからです。その家族を患者さん自身がみていました。事情を伺い、ご家族がショートステイを利用できるように調整したことがあります。
行沢さん:この患者さんは、定期的な入院が必要な状況でしたが、ご家族のことが気がかりになっていました。担当のケアマネジャーと連携して施設を探し、ご家族に一時入所していただくことができ、患者さんも「ここなら家族を任せても大丈夫」と思える施設が見つかったことで、ご自分も安心して治療を続けることができた例です。
利用できる支援制度を総合的に検討し伝えます
行沢さん:治療に関するお金の相談は本当に多いです。最も多いのは「一か月の医療費はいくらかかるのか?」という相談です。まずその方の具体的な医療費を計算してみて、高額療養費(制度)など、制度を利用することで支払い額がどの程度になりそうかを検討します。
当院では支払いが難しい場合は分割払いの相談を受けますが、それでも難しい場合は生活保護、あるいは無料低額診療も選択肢になります。無料低額診療事業とは、生計が困難な方に向けた国の事業で、認定された医療機関が、無料または低額で診療を行うことができる仕組みです。当院で無料低額診療を受ける場合、生活保護基準の120%以内の収入が目安となります。高齢者の一人暮らしで、月14~15万円程度の収入なら対象になることがあります。ただし、貯蓄や加入中の保険なども確認したうえで、利用できるかどうかを判断します。
剱持先生:無料低額診療事業を使える人は限られますし、院外の保険薬局の費用は対象外ですから、がん保険や障害年金など、ほかに利用できるものを確認する必要があります。
無料低額診療事業について(北海道の場合)
※本事業の詳細や実施医療機関については、お住まいの都道府県や市区町村のホームページ等でご確認ください。
行沢さん:お金に関する相談は、患者さんご自身だけでなくご家族から寄せられることもあります。「子どもの学費や住宅ローンを抱えているが、治療費をどう工面すればいいのか?」といった切実な声です。そうした場合は、単に医療費の説明にとどまらず、障害年金や傷病手当金、労災など、利用可能な支援制度を総合的に検討します。
対話を通じてプロフェッショナルが悩みを紐解く
剱持先生:私は呼吸器内科なので職業性肺疾患の観点からも、患者さんの職歴を丁寧に伺うことも意識しています。たとえば、過去にアスベスト関連の仕事をしていた肺がんの患者さんであれば、労災認定により補償制度が利用できることもあります。医療者が制度のことを理解し、意識して患者さんのお話を聞くことによって、生活の中に隠れている制度につながるヒントを見つけることが多いです。
岡本さん:ちょっとしたことでも、何でも良いのでお話しいただければ、制度を活用して治療を続ける道を一緒に探せます。相談することで新しい選択肢が見える、ということをぜひ知っていただきたいですね。
山下さん:私たちリハビリの専門職も、患者さんの精神面に気を配りながら、基本的にはどんなお話でも伺います。
行沢さん:患者さんがリハビリ中に「明日退院なんだけど、医療費が払えそうにない」とセラピストに打ち明けてくださったことから、私たちソーシャルワーカーにつながり、無事に支援を受けて頂くことができたケースもありました。
剱持先生:患者さんは「先生にお金が心配だと話をしたら、治療を止められてしまうのでは」と思うこともあるそうですが、本当に大事なのは「まず相談すること」です。医師に言いにくければ、看護師でもソーシャルワーカーでもセラピストでも構いません。誰かに話してくれれば、必ず専門のスタッフにつながります。
チーム医療は全国的にも盛んですから、がんで受診されている病院の多くでは、当院と同様のサポートが期待できると思います。
仕事をやめてしまう前に、ためらわずに相談を
岡本さん:病気になっても治療を継続するためには、生活が安定し収入を維持することも大切で、仕事を続けることはとても重要です。また、がんと診断を受けてすぐ「会社に迷惑をかけたくない」と、“びっくり離職”(がんと診断されたショックで突然退職)してしまう方がいます。
すぐにはやめず、職場や医療者、家族や周囲の方に相談しながら、続けていく方法を考えてほしいなと思います。以前、運送業の方で、運転はできなくなったものの、事務職に配置転換してもらって仕事を続けられた例もあります。
現在はがん治療も進歩し、さまざまな支持療法や対処療法がでてきました。がんと診断されてから自分自身の生活にあった方法で治療を続けることができたりします。
まずは、離職を早まらずに、こちらに相談していただきたいです。
剱持先生:仕事を辞めてしまってから後悔することのないようにしてほしいと切に思います。会社に籍があるからこそ使える制度もあるからです。“びっくり離職”を防ぐため、私は診断直後に「今は大きな決断をしないで、じっくり相談していきましょう」と必ず伝えています。
山下さん:入院時のリハビリテーションで患者さんに確認すると、「仕事を続けたい」と仰る方がとても多いです。しかしながら、治療を継続していく中で体力が落ちてしまって、仕事を続けられなくなってしまう方もいます。まずはリハビリで体力をつけられるよう支援し、いまの自分の状態でどこまでやれそうかイメージしてもらい、仕事の内容と患者さんの身体面の状況から配置転換などを含めて一緒に考えるようにしています。「体力や症状に応じて今の仕事を続けられるか、休憩をはさめば可能か」など、患者さん自身の体力が持つレベル感(できる範囲)を把握して、場合によっては負荷を減らして「働き続けられる」という見通しを持てることが、患者さんの治療意欲や安心感につながると思います。
仕事に子育て、介護など。
さまざまな役割を持つあなたにこそ、がん相談支援センターを頼ってほしい
岡本さん:乳がんの患者さんでは、やはり子育てしながら治療をされている方は多いです。夏休みに入ったお子さんと一緒に来院し、ご自分は治療を受けながらお子さんの宿題をみていた姿がとても印象に残っている患者さんがいました
また、子育て世代の方は仕事を持っている方も多いので、「穴をあけて職場に迷惑をかけたくない」「病気のことは隠して働いている」など、さまざまな事情を持ちながら治療をしている方もいます。そういったお話も、誰にもできないとつらいですから、「ひとりで抱えず、相談して」と伝えたいですし、“こころの安全”が担保できる、安心して話せる場所が医療機関にあると知ってほしいですね。
山下さん:リハビリの場面でも「親の介護もある」「就学している子どもがいる」という声はよく聞きます。そういったご家庭ではお金の悩みにもつながってくるので、そうした声を他のスタッフと共有し、必要かつ適切な支援につなげています。
剱持先生:リハビリのスタッフが生活動作を検討し、看護師が生活状況を把握し、薬剤師が副作用を確認する、など、院内のそれぞれの職種がしっかり自分の役割を果たしてくれています。そして、それぞれの情報が共有され、患者さんの治療や生活支援に活かしています。
治療しながら「あなたらしく生きる」を応援します
読者の方へのメッセージをお願いします
山下さん:リハビリの場面では、ほんの小さな不安や悩みを打ち明けていただいています。まずは気軽に、どんなことでも声をかけてみてください。そこから、一緒に前へ進むお手伝いをしたいと思っています。
岡本さん:「こんな話をしていいのかな」と思うことも、大切な情報ですので、遠慮せず、安心して声をかけてください。私たち看護師からも声をかけて、患者さんやご家族の気持ちに寄り添いながら、伴走していきたいと思います。患者さんがその人らしく過ごせるよう支援していきたいです。
行沢さん:そもそもソーシャルワーカーの仕事は、その人らしく生活するための支援だと思っています。人それぞれ幸福感も違うので、今後もその人らしさを尊重して、私だけではできないことは他の職種とも一緒になって支援していけたらと思います。
相談したからといって、すぐにすべて解決できるとは限りません。でも、話すことで気持ちが整理され、少し楽になることは必ずあります。ぜひ一度、誰かを頼ってみてほしいですね。
あなたも「チーム医療」の大切な一員です。一緒に考えていきましょう。
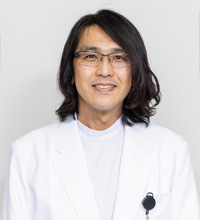
剱持 喜之 先生
病気や治療以外のことについて、病院で相談してもよいことなのか、わからない患者さんは多いと思います。ご自分から言い出しにくいと思われるような、お金や仕事の話などは私から伺うようにしています。医師から聞かれた経験があれば「これは先生に相談してもいいことなんだ」と捉えてくださることもあるからです。
がんと向き合う旅路は、患者さんや周囲の方々も、医療者と一緒に歩むものです。つまり、みなさんも“チーム医療”の一員なのです。ぜひ、思いや不安を医療者に伝えてください。一緒に解決できる方法を探しましょう。
また、診断を受け治療が続いていく中で、体調だけでなく、気持ちや状況がどんどん変わっていくことと思います。大変なこと・心配なことがあれば、いつでも遠慮なくお話しください。治療を続けていくために必要なことと、あなたの希望や想いの両方を、うまく調整しながら“あなたらしい生き方”や病気と向き合える形を一緒に見つけていきたいと思います。
2025年10月公開
